今回は、女子サッカークラブ「FC PAF」監督就任の経緯や初の女子サッカーをテーマにした本を書き上げる上での裏話などを語ってもらいました。
監督就任の舞台裏
兼正(以下K)
おじさんは現在も女子サッカークラブの監督をしていますが、きっかけはなんだったんですか?
良之(以下Y)
ベースボールマガジン社を辞めて、前の編集長だった橋本さんていう方と一緒に仕事をやろうってことになったんだ。それでアンサーって会社に入ったんだよ。
K
83年頃のお話しですか?
Y
そう、そのとき大原がアンサーで社員として働いていた。サッカーをやっているのはもちろん知っていたんだけど、「監督がいなくて、試合前にメンバー表書く人がいないんです」って言っていて(笑)。「試合前にメンバー表を書くだけなら引き受ける」よって返事をして、84年に行き始めたんだ。
K
「女子サッカー界に貢献するために」とかではなかったんですか?
Y
女子サッカーがどうのって言うよりも、一生懸命頑張っている選手たちがいて、その選手たちが困っているから「じゃあ、可能な範囲で協力するよ」っていう軽い気持ちだった。それをいままで28年間も続けるとは思ってもいなかった。「FC PAF」っていうチームで、当時は実践女子大の卒業生で構成されていた。
K
おじさんが直接的に女子サッカーに関わるようになったのはそれからですか?
Y
そうだね、監督を引き受けて関わるようにはなったけど、取材に行っても仕事で扱えるようなものは当時はなかったよ。足かけ30年近くになるわけだけど女子サッカーの普及や発展に貢献した、とは自分では思わないな。さっきも言ったように80年代の女子サッカー発展に貢献したのは、僕の後を継いで「サッカーマガジン」の編集長を務めた千野(圭一)だね。
初の女子サッカーをテーマにした著書制作の舞台裏
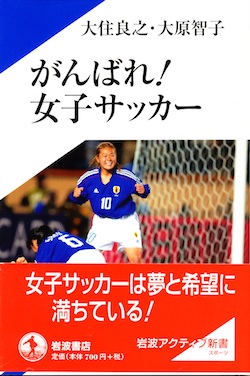
K
おじさんは岩波書店から『がんばれ! 女子サッカー』という新書を出していますが、それはどういった経緯で?
Y
04年のことだね。これはね、アテネオリンピックの女子サッカーアジア予選で日本が北朝鮮に勝って予選突破を決めて、すごく盛り上がったんだよ。東京の国立競技場で行われたんだけど、オリンピック出場がかかった北朝鮮戦はテレビ朝日で生放送され、視聴率16.3%、瞬間最高視聴率31.1%。
K
凄いですね。
Y
いまはなでしこJAPANも人気になったから大した数字じゃないかもしれないけれど、当時はまだ知名度もあまり高くないなかでのその視聴率だからね。その北朝鮮戦がもの凄い試合だった。7連敗中の相手に対して3-0の快勝。その試合をテレビで観て感動した岩波の編集者が「女子サッカーの本を出せませんか」って連絡をしてきたんだ。
K
なるほど、そういう経緯で。
Y
すぐに打ち合わせに行ったんだけど、出版社側からどうせならオリンピック(8月)前に出したいっていう提案があってね。そりゃそうだ。オリンピックで惨敗だったら、熱気も消えてしまうからね。それでいきましょうってことになったんだけど、実はちょっと不安があったんだ。
K
どんな不安ですか?
Y
その年の夏は僕がほとんど日本にいない予定になっていたんだよね。5月の終わりにUEFAチャンピオンズリーグの決勝を観にドイツに行って、そのあと日本代表がイングランドで試合するから、帰国せずにそのまま残って取材して。
K
小野伸二がゴールを決めた試合ですよね。
Y
そうそう、その試合。帰国したら1週間ほどでポルトガルで行われる欧州選手権(EURO)を取材。戻って7月中旬からは中国でのアジアカップの取材。8月8日に北京で決勝戦が終わって日本に帰ってきた翌日にはアテネオリンピックに出発という日程だった。
K
ハードですね。ただオリンピック前の発売だと、制作スケジュールとしては7月半ば校了くらいのイメージですかね。執筆期間が短い(笑)。
Y
そうだね、相当短かった(笑)。しかも僕は日本にいないんだから。それで打ち合せの席に大原を連れて行ったんだ。大原には「一緒に打ち合わせに行くよ」ってだけ言って。その席で僕が「ふたりで書きますから大丈夫です。共著でどうでしょうか」って言っちゃって(笑)。大原がびっくりしていたよ、「なにを言い出しているの!?」って(笑)。
K
(笑)。そしてできあがったのがこの本ですね。
Y
当時、女子サッカーを包括的に紹介する本ってまだなかったからね。日本の女子サッカーの歴史や世界の女子サッカー史を追った本なんてさ。ただ、それだけを書くと完全な資料本になってしまうから、最後は同年齢で日テレ・ベレーザと女子日本代表の両チームで中盤のコンビだった澤穂希と酒井與惠両選手の対談を入れたりして。
K
これも大原さんに任せて......。
Y
さすがに出席したよ(笑)。
(次回に続く)
横浜、2012年12月6日―。来年で誕生150年を迎えるサッカーの歴史のなかに大きく残る日だ。
サッカーで初めて公式に「ゴールラインテクノロジー(GLT)」が使われたのだ。ボールがゴールにはいったかどうかを見きわめて主審に伝達するシステム。試合はクラブワールドカップのサンフレッチェ広島対オークランド(ニュージーランド)。主審はアルジェリアのジャメル・ハイムディだった。
現在国際サッカー連盟(FIFA)が認可しているGLTは、特殊なボールとゴール内に張った磁場を利用した「ゴールレフ」と、何台かの高速ビデオカメラを使う「ホークアイ」の2種類。横浜ではゴールレフ、同大会の4試合が行われる豊田ではホークアイが設置されている。
その名のとおり、GLTが使われるのは、ボールがゴールにはいったかどうかの見きわめに限られる。タッチアウトやオフサイド、ファウルなどには一切関与しない。
これまでのところ、クラブワールドカップではGLTが必要になるような際どい場面はないが、大会の残り5試合でそうした場面が生まれれば、日本のファンは「新時代」の証人となる。
さて、「サッカーでも機械判定が登場」などと紹介されるGLTだが、少し違う。
「キックオフの90分前にその試合の担当審判がチェックし、GLTを使うかどうかを審判自身が決める」とFIFAのバルク事務総長は説明する。大金をかけて導入しても、実際に使うか使わないかは審判に任されているというのだ。
「GLTも審判を助ける道具のひとつ」と話すのは、2010年ワールドカップで活躍した西村雄一主審だ。
「主審の腕につけた装置で副審から注意を喚起するシグナルビップや、審判員間で会話ができる無線システムなどと同じように、正しい判定をするための助けになるよう導入されたものなのです」
GLTは主審の腕時計に「ゴール」の信号を送るが、それを採用するもしないも主審に任されているという。最終判断を下すのは、あくまで審判なのだ。
絶対に勝てるシステムや戦術がないのは、サッカーが「ヒューマンゲーム」だからだ。主体が人間であることにこそ、サッカーの最大の魅力がある。
GLT導入は歴史的な出来事。しかしゴール判定が人間不在になったわけではない。最終判断は、いまも審判という人間に任されている。
(2012年12月12日)
「『良いクロス』って何だろう?」
コーヒーを飲みながら、友人とそんな話をした。「清武がヨーロッパでベストクロッサーに選ばれた」という話を聞いたからだ。
1960年代のダービー(イングランド)にアラン・ヒントンという選手がいて「ベストクロッサー」と称賛されていたのを思い出した。味方に得点させるためにサイドから中央に送るパスを「クロス」と呼ぶ。ヒントンは正確なキックで定評があり、そのクロスから数多くの得点をアシストした。
ドイツのニュルンベルクに所属する清武弘嗣。今季15試合のチームゴール14のうち、自ら3点を記録しただけでなく、実に5点をアシストしている。味方の頭にぴたりと合う彼のクロスこそ、このチームの生命線だ。
確かに得点に結びついたクロスは良いものに違いない。だがテレビ解説者が「良いクロスですね」と言うのを聞くと、最近、どうも結果論のように聞こえてならない。
クロスの多くは長身の相手DFにはね返される。狙いどおりのところにすばらしいボールを送ったと思っても、相手DFのポジショニングや対応が良ければシュートにさえ結びつかない。
攻撃側はニアポスト(クロスを入れる選手に近い側)とファーポスト(遠い側)に少なくともそれぞれ1人詰めるのが原則。ボールがけられるタイミングに合わせてそこに走り込む約束になっているから、ける側もイメージしやすい。だが当然のことながら相手チームもそこをしっかりと防ぎにかかるから、簡単ではない。
清武の場合、比較的高いボールがゴール正面、相手DFとDFの間に落ち、そこに走り込んだ味方がヘディングで得点するというアシストが多い。GKが出てこれず、しかもできるだけゴールに近い場所に落とさなければならない。超精度のキックが必要だ。
だがいくら正確なキックでも、それだけでは得点は生まれない。走り込む選手が清武から送られてくるボールのコースや特性特質を知り抜き、どんぴしゃりの場所とタイミングでジャンプしなければならないからだ。
「結局、『良いクロス』というものは存在しない。キッカーと詰める選手の、正確な技術と高度な相互理解による連係プレーがあるだけではないか」
私の結論に、友人は「何をいまさら」という顔をしながら、「サッカーはすべてそうだよ」と言った。
(2012年12月5日)